問8
A令和 5 年度の老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを上回ったことから、令和 5 年度において 67 歳以下の人(昭和 31年4月2 日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を、令和5 年度において 68 歳以上の人(昭和 31年4月1 日以前生まれの人)は物価変動率を用いて改定され、満額が異なることになったため、マクロ経済スライドによる調整は行われなかった。
B 令和 5 年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成 29 年度に引き上げが完了した上限である 16,900 円(平成 16 年度水準)に、国民年金法第 87 条第 3 項及び第 5 項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。
C 保険料の 4 分の 3 免除、半額免除及び 4 分の 1 免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。
D 昭和 36年4月1 日から平成4年3月 31 日までの間で、20 歳以上 60 歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、そ の期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
E 保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付 に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4 月 1 日以降、国庫負担割合が 3 分の 1 から 2 分の 1 へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
問8 解答
正解 C (難易度:B)
A:× 誤り。老齢基礎年金の額は、マクロ経済スライドの規定に基づき、名目手取り賃金変動率と物価変動率の両方を参照して改定されます。ただし、実際の改定率は、これらの変動率だけでなく、政策判断や国会での議論によっても影響を受ける可能性があります。また、満額が異なることになったとしても、マクロ経済スライドによる調整が行われなかったと断言することはできません。
B:× 誤り。国民年金保険料の月額は、過去の引き上げが完了した上限額に基づいて設定されますが、実際の保険料額は毎年度、名目賃金の変動に応じて改定される可能性があります。ただし、令和5年度の実際の保険料額が名目賃金の変動に応じて改定されたかどうかは、具体的なデータを参照する必要があります。
C:○ 正しい。保険料の免除を受けた場合、免除されていない部分(残余の額)が納付されていなければ、追納することはできません。免除された部分の保険料を追納するためには、まず免除されていない部分が完全に納付されている必要があります。
D:× 誤り。昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間に20歳以上60歳未満の学生であった期間は、任意加入期間とされていましたが、この期間に加入せず保険料を納付しなかった場合、その期間は合算対象期間とされますが、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されないことが一般的です。
E:× 誤り。全額免除期間について、免除された保険料を追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるのは正しいですが、国庫負担割合が2分の1に引き上げられたのは平成26年からです。また、年金額の反映割合が免除の種類に応じて異なるという記述は誤りです。免除された期間は全額免除であっても、老齢基礎年金の計算において保険料納付済みとして扱われます。
解説参照資料:国民年金法、関連する厚生労働省令、判例、国民年金制度解説資料。

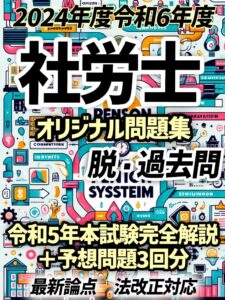

コメント