問7
A 老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。 1 人当たりの金額は、第 2 子までは配偶者の加給年金額と同額だが、第 3 子以降は、配偶者の加給年金額の 3 分の 2 の額となる。
B昭和 9年4月2 日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なく なる。
C甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2 級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合し た障害の程度が障害等級 1 級と認定される場合、新たに障害等級 1 級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。
D乙は、視覚障害で障害等級 3 級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級 1 級又は 2 級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする。)を受給している。現在も、厚生年金保険の適用事業所で働いているが、新たな病気により、障害等級 3 級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても、障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、厚生年金保険法第48条の規定により、前後の障害を併合した障害等級 2 級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
E 障害手当金の額は、厚生年金保険法第 50 条第 1 項の規定の例により計算した額の 100 分の 200 に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金 2 級の額に 2 を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。
問7 解答
正解 C (難易度:B)
A.× 子の加給年金額については、その対象となる子の数に応じて加算されますが、1人当たりの金額が第2子までは配偶者の加給年金額と同額で、第3子以降が配偶者の加給年金額の3分の2になるという規定はありません。子の加給年金は、対象となる子ごとに一定額が加算されます。
B.× 老齢厚生年金の受給権者に対する配偶者の加給年金に特別加算が行われる規定は存在しません。配偶者の加給年金は、受給権者の配偶者が一定の条件を満たす場合に支給されるもので、生年月日による特別加算の規定はありません。
C.○ 甲が障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給しており、新たに障害等級2級に該当する障害が生じた場合、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定されると、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生し、障害厚生年金の額も改定されます。これは障害の程度が重くなったことを反映し、より高い障害等級に応じた給付を行うための規定です。
D.× 乙が障害等級3級の障害厚生年金を受給している状態で新たな障害が生じ、障害等級2級に該当する場合、障害厚生年金の額が改定される可能性がありますが、従前の障害厚生年金の受給権が自動的に消滅するわけではありません。障害の状態や障害等級が変わった場合、障害厚生年金の額の見直しを行い、障害の程度に応じた適切な給付が行われます。
E.× 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項により計算された額の100分の200に相当する額であるという規定はありません。障害手当金は、障害基礎年金とは別に定められた給付であり、その計算方法や額には特定の規定があります。

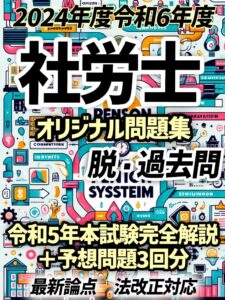

コメント