問1
A 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
B 労働基準法の労働者は、民法第 623 条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。
C 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。
D 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
E 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。
問1 解答
正解:E (難易度:B)
1.× Aの記述は誤りです。労働基準法の労働者とは、現に労働契約に基づき労働を提供している者を指します。失業して求職活動をしている間は、労働契約の下で労働を提供しているわけではないため、労働基準法の労働者ではありません。
2.× Bの記述も誤りです。民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者は労働基準法の労働者に該当しますが、実質的に使用従属関係にある場合は、請負契約の形式をとっていても労働基準法の労働者に該当することがあります(関連判例:最高裁判所昭和63年6月10日判決)。
3.× Cについても誤りです。同居の親族のみを使用する事業で一時的に親族以外の者が使用されている場合でも、その者が使用者の指揮命令を受けて労働を行っているならば、労働基準法の労働者に該当します。
4.× Dは誤りです。株式会社の代表取締役は、一般的には使用者側の立場にあるため、原則として労働基準法の労働者にはなりません。ただし、特殊な状況下で労働者としての性質を有する場合も考えられますが、これは例外的な状況です。
5.○ Eは正しいです。明確な契約関係がなくても、実質的に事業に使用され、その対償として賃金が支払われる者は、労働基準法の労働者に該当します。この点は、労働基準法第9条において労働者を「事業者に使用される者」と定義していることからも明らかです。
【解説参照条文】
労働基準法第9条(労働者の定義)
民法第623条(雇用契約)
関連判例:最高裁判所昭和63年6月10日判決(使用従属関係に基づく労働者の判定)
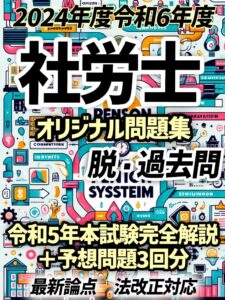
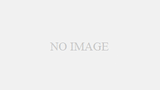

コメント