1 質権設定当時、乙土地上にX所有の建物があった場合、当該質権の効力はその建物には及ばない。
2 質権を設定した後、Xが乙土地をZに売却した場合、ZはYの質権に取り償える義務がある。
3 質権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の本金以外の費用(遅延損害金や弁済費用など)は、当該質権によって担保される。
4 Yの質権は、Xに対しては、被担保債権の利息が存在していても、時効によって消滅する場合がある。
問4 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 解説:
日本の民法の規定によれば、質権はその目的物の持ち主から質権者へと物の所在を移転することで設定される。もし、質権の設定当時、乙土地上にX所有の建物があった場合、原則として、当該質権の効力はその建物にも及ぶことになる。したがって、この選択肢は不正確である。
2.○ 正しい
乙土地に質権を設定した後で、Xが乙土地をZに売却した場合、Zはその土地を質として持つYに対して取り償える義務が生じる。これは質権が設定された物件が第三者の手に渡った場合、質権者の権利を保護するためのものである。
3.× 解説:
通常、質権の設定行為において特別な合意がない限り、被担保債権の本金だけが当該質権によって担保されるものと解されます。その他の費用(遅延損害金や弁済費用など)が質権によって担保されるかどうかは、当事者間の合意に依存します。
4.× 解説:
質権は担保権の一つであり、その権利の存在は被担保債権の存在に依存する。しかし、被担保債権の利息が存在していても、時効によって質権が消滅するというのは一般的な解釈とは異なる。被担保債権が時効によって消滅した場合、質権もその効力を失うことになるが、利息の存在自体が質権の消滅を引き起こすわけではない。
この解説に基づき、選択肢2が最も適切なものとなります。


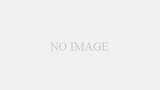

コメント